 |
 |
「三九郎(さんくろう)」はもと宮中の行事で「左義長(さぎちょう)」と言われ、青竹で作った3本の毬打(ざつちょう)を組み合わせたものに正月の門松、しめ飾り、書き初めなどを飾り、1月14日または15日にこれを焼き、その年中の病を除くことを願ったものと伝えられています。
三九郎という言い方は主に松本地方で呼ばれているもので、道祖神祭りと結びつき、小正月に今でも各地で行われている子供たちの年中行事です。小学生が中心となって家々から集めた門松、しめ飾り、だるまなどを燃やし、その火でまゆだま(米の粉で作っただんご)を焼きます。これを食べれば虫歯にならないといわれています。地方によってどんど焼き、さいと焼き、おんべ焼き、おにび、ほっけんぎょうなどと呼ばれています。(取材・中村 健)
 |
 |
ここで紹介する三九郎は長野県のほぼ中央、山形村・中大池地区(松本市の郊外)のものです。伝統を守って子供たちが中心となり、今年も1月15日に行われました。
 |
 |
 |
準備が大変
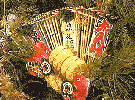 |
 |
 |
門松やしめ飾り、そして一年間、家内安全を守ってくれたダルマ。それから、よく燃える豆がら。
 少しでも高く |
 中に入れるんだよ |
 完成だあ! |
 道祖神に向かって |
 安全無事を |
 さあみんなを呼びに行こう |
「さんくろやい、さんくろやい、じいちゃんばあちゃん孫つれて、おだんご焼きに来ておくれ」
 そろそろ日も暮れて |
 みんなおだんご持って |
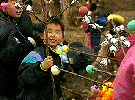 集まってきたよ |
 さあ火をつけるぞう |
 それっ、火がついた |
 |
 わあ、すごーい、 |
 風にあおられて、 |
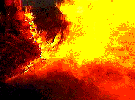 もえる、もえる |
 上のだるまに |
 火がつくぞう! うわあ、 |
 だるまが落ちるう! |
 |
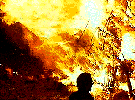 |
 |
残りのさんくろうにも火がつけられ、祭りは盛り上がります
 |
 |
 |
火がおさまったところを見はからって、さあ、おだんごを焼こう。今年も一年げんきでありますように…